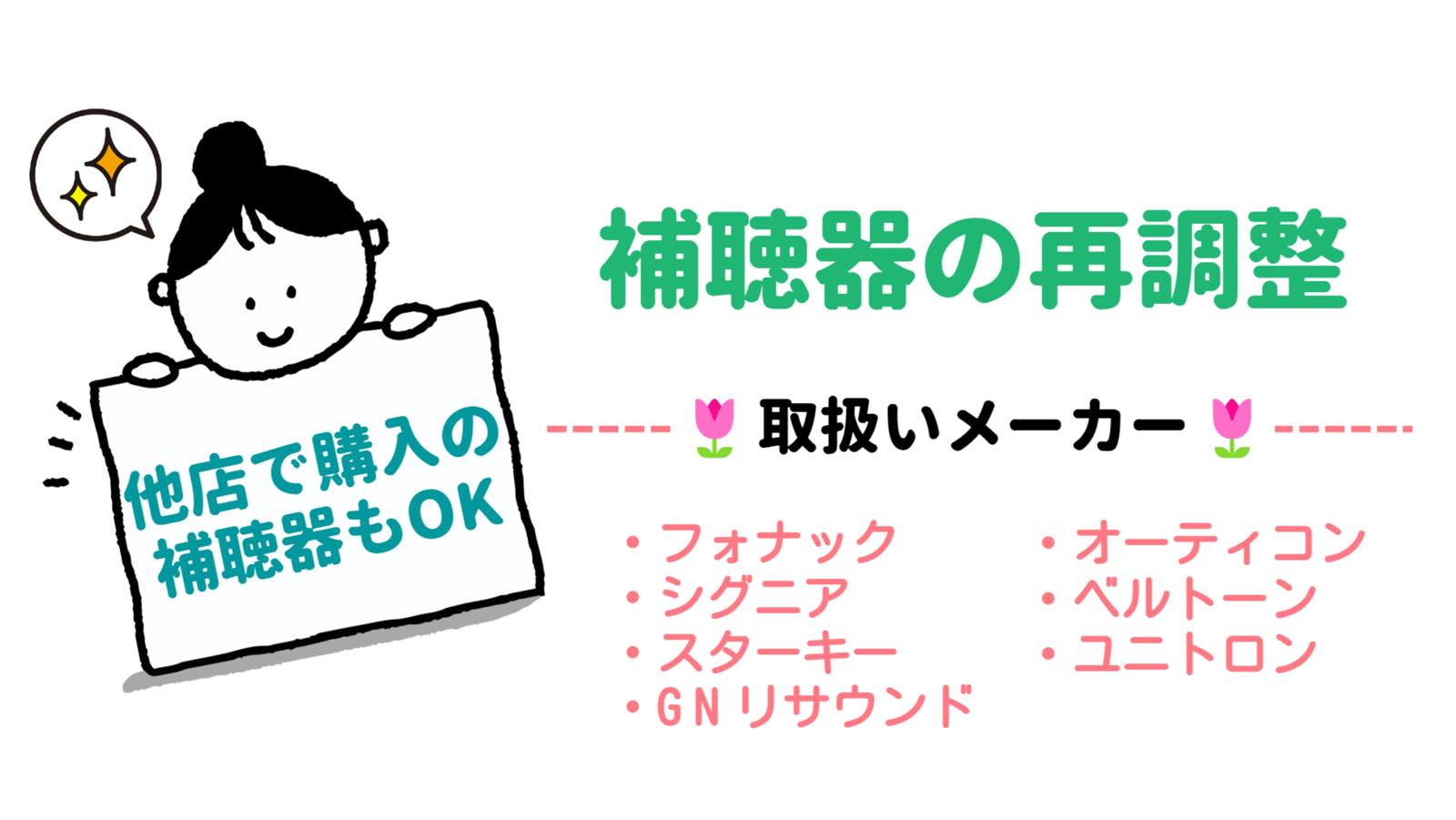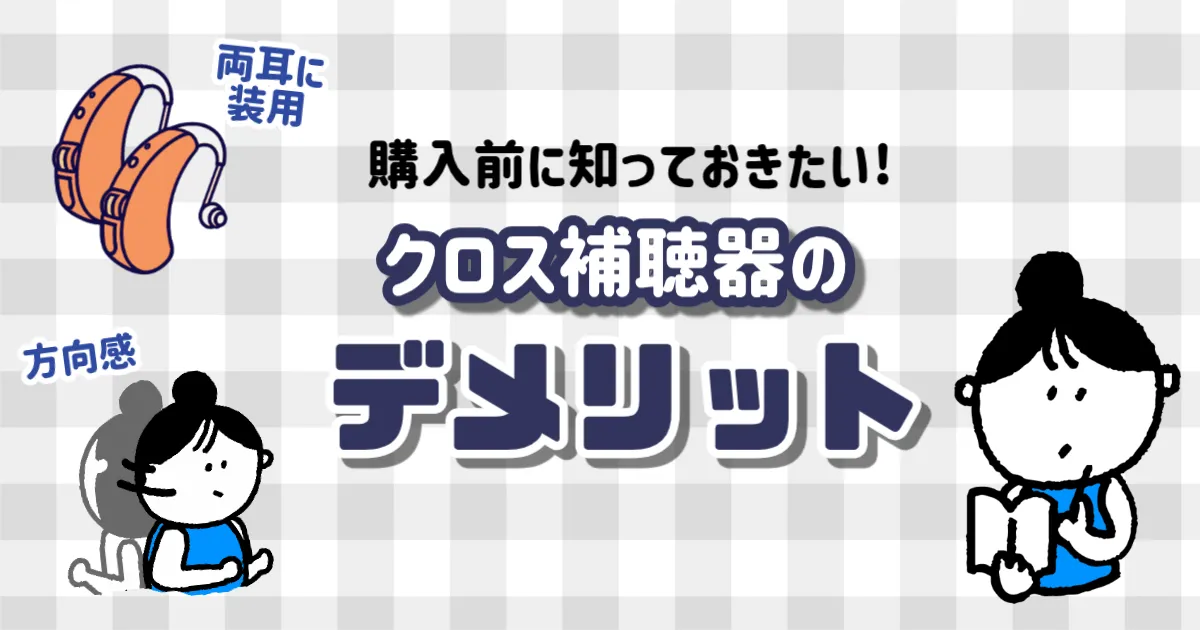こんにちは!秋葉原補聴器リスニングラボのハヤシです。当店では片耳難聴でお悩みの方に「クロス補聴器」をご提案することが多いのですが、購入を検討される際には、メリットだけでなくデメリットもしっかり理解しておくことが大切です。今回は、クロス補聴器のデメリットと購入前に知っておきたい注意点について、くわしくお伝えします。
 たろうくん
たろうくんみみちゃん、実は耳が聞こえにくくて耳鼻科に行ったんだ。そしたら片耳難聴だって言われちゃった😟 片耳難聴向けの補聴器ってあるのかな…?
 みみちゃん
みみちゃんそれは大変だったね。片耳難聴向けには『クロス補聴器』っていうものがあるみたいだよ!聞こえない耳の音を、聞こえる耳に送ってくれる仕組みなの✨️
 たろうくん
たろうくんクロス補聴器か…でも補聴器って高いよね?😥 それに、どこで買ったらいいんだろう。どうやって選んだらいいかもわからないよ…失敗したくないし💦
 みみちゃん
みみちゃん買う前に、メリットだけじゃなくてデメリットも知っておきたいよね。まずは一緒にネットで調べてみましょう✨️しっかり情報収集してから決めれば大丈夫だよ!
クロス補聴器とは?基本を押さえよう

クロス補聴器(CROS補聴器)は、片方の耳が聞こえにくい「片耳難聴」の方のための特殊な補聴システムです。通常の補聴器とは異なり、聞こえない耳側から音を拾い、聞こえる耳側へ音を伝えるシステムになっています。
たとえば、右耳が聞こえず左耳が正常な場合、右耳側にはCROS送信器を、左耳側には受信機となる補聴器を装着します。これにより、右側からの音も左耳で聞くことができるようになります。
「片耳が聞こえないだけなのに、なぜ両耳に装置が必要なの?」とよく質問を受けますが、これがクロス補聴器の基本的な仕組みなんです。

クロス補聴器の主なデメリット

クロス補聴器には多くのメリットがありますが、購入を検討される際には、以下のデメリットもしっかり理解しておくことが大切です。
両耳装用の必要性
見た目の懸念
クロス補聴器の特徴的なデメリットの一つが、両耳に装置を装用する必要があることです。片耳だけが難聴でも、両耳に装置をつける必要があるため、外見上の違和感を感じる方もいらっしゃいます。
当店にご来店されるお客さまからも「人に会う機会が多いので、両耳に装置をつけるのは抵抗がある」というお声をよく聞きます。最近の機器は小型化が進んでおり、以前よりも目立ちにくくなってきていますが、それでも両耳装用という事実は変わりません。
費用面の負担
両耳分の機器が必要なため、初期投資が大きくなる傾向があります。具体的には、CROS送信器と受信器(補聴器)をセットで使用するため、片耳だけの補聴器よりも購入費用が高くなります。
令和7年現在、クロス補聴器のセットは、メーカーや機能によって価格に幅がありますが、一般的に通常の補聴器(片耳分)よりも高額になることを念頭に置いておく必要があります。
音の方向感覚の問題
難聴側の音を反対の良聴耳で聞くことになるため、音がどちらの方向から来ているのかを正確に把握することが難しくなります。
たとえば、左耳が難聴で右耳が正常な場合、左側から誰かが呼びかけても、その音は右耳で聞こえるため、反射的に右を向いてしまうことがあります。慣れで多少改善することもありますが、根本的な解決は難しい課題です。
バッテリーの消費が早い
クロス補聴器は、通常の補聴器よりもバッテリーの消費が早い傾向にあります。これは、音を送信するための無線技術を使用しているためです。
電池式の場合、通常の補聴器より電池交換の頻度が高くなります。充電式タイプの場合も、毎日の充電が欠かせません。営業職など外出が多い方や長時間の使用が必要な方は、変えの電池や充電器の準備を検討するとよいでしょう。
悪い側の耳の聴力を補えない
これはよく誤解されているポイントですが、クロスシステムは聞こえない側から聞こえる側へ音を伝える仕組みです。クロス送信器には、音声を集めて反対側の受信器に送信する機能しかないため、送信器をつけた難聴側の聴力や聞こえを改善することはできません。
「クロス補聴器をつければ聞こえない耳も聞こえるようになる」と期待される方もいらっしゃいますが、残念ながらそうではありません。「聞こえない耳を治す」というわけではなく、「聞こえない側からの音を活用する」ためのものです。
慣れるまでに時間がかかる
新しい聞こえ方に慣れるには時間がかかることがあります。とくに、これまで片耳だけで聞いていた方が、突然360度からの音を認識できるようになると、最初は音の洪水に感じられることもあるでしょう。
最初は『うるさい』と感じる方もいらっしゃいますが、脳が新しい聞こえ方に適応するまで、2週間から1ヶ月程度かかることがあります。少しずつ装用時間を伸ばし、聞こえに慣れていくことが必要です。
購入前の重要な注意点
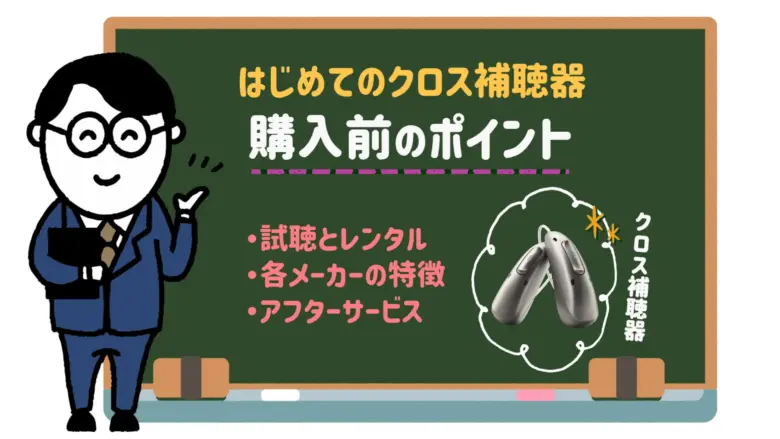
無料レンタルを活用しましょう
クロス補聴器を購入する前に、実際に試してみることをオススメします。当店では2週間の無料レンタルを実施しており、実際の生活環境で使用感を確かめていただけます。
この期間に、デメリットが自分にとって許容できるものかどうかを判断することが大切です。レンタル期間中に、「会議中の聞こえはどうか」「外出時に困ることはないか」など、様々なシーンで試していただくと良いですね。
各メーカーの特徴を比較する
当店では、フォナック(スイス)、オーティコン(デンマーク)、シグニア(ドイツ)、リサウンド(デンマーク)、スターキー(アメリカ)など、世界的なメーカーのクロス補聴器を取り扱っています。各メーカーによって音質や使い勝手、デザインなどが異なりますので、複数のメーカーを試してみるのもいいですね。
アフターサービスを確認する
クロス補聴器は購入して終わりではなく、定期的な調整や清掃、故障時の対応など、継続的なサポートが必要です。購入を検討している店舗のアフターサービスについて、事前によく確認しておきましょう。
- 無料で調整してくれるか
- 故障時の対応はどうなるか
- 保証期間はどれくらいか
- 店舗の立地は通いやすいか
これらのポイントは、長く快適に使い続けるために非常に重要です。
デメリットを克服するためのヒント
クロス補聴器のデメリットを理解した上で、それをどう克服するかを考えていきましょう。
両耳装用の見た目について
最近のクロス補聴器は、非常に小型化が進んでいます。また、補聴器のカラーを髪色に合わせて選ぶことで、さらに目立ちにくくなるんです。
また、「補聴器をつけていることを隠す」という考え方から一歩進んで、「必要なものを使っている」というポジティブな捉え方をされる方も増えています。カラーバリエーションが豊富な製品もあり、ファッションの一部として楽んでいらっしゃる方もいます!
費用面の負担について
確かに初期投資は大きいですが、長期的に見ると生活の質を大きく向上させる投資と考えることができます。また、自治体によっては補聴器購入の助成制度があることもあります。
令和7年現在、東京都内の多くの区では、補聴器購入に対する助成金制度を設けています。金額は区によって異なりますが、数万円の助成が受けられる場合もあります。お住まいの地域の制度を確認してみると良いでしょう。
音の方向感覚の問題について
クロス補聴器の音の方向感覚の問題を克服するには、まず「慣れ」が大切です。最初は短時間から使い始め、徐々に装用時間を延ばしていくことで脳が新しい聞こえ方に適応しやすくなります。
自宅など静かな場所からスタートし、慣れてきたら外出先や騒がしい環境でも使ってみましょう。また、補聴器店で定期的に相談しながら調整を重ねることで、自分に合った使い方や設定が見つかります。焦らず段階的に使い続けることが、音の方向感に慣れるコツです。
バッテリー消費について
充電式タイプを選ぶと、毎日の充電は必要ですが、電池交換の手間やコストを削減できます。外出が多い方は、バッテリー付きのケースを選んだり、予備のバッテリーを持ち歩いたりする対策が有効です。
慣れるまでの期間について
新しい聞こえ方に慣れるには時間がかかりますが、徐々に使用時間を増やしていくことで、脳が適応していきます。最初は静かな環境で短時間使用し、徐々に騒がしい環境や長時間の使用に移行していくと良いでしょう。
最初は1日2〜3時間の使用から始めて、少しずつ時間を伸ばしていくことをオススメしています。
クロス補聴器の選び方
クロス補聴器を選ぶ際のポイントをいくつかご紹介します。
実際に聴き比べる
補聴器は「試着」だけでなく「試聴」が非常に重要です。複数のメーカーやモデルを実際に装着して、音質や装用感を比較しましょう。
当店では、フォナック、オーティコン、シグニア、リサウンドなど、世界的なメーカーのクロス補聴器を取り揃えています。それぞれ音質や機能に特徴がありますので、複数試して比較してみるといいですね。
生活スタイルに合わせた選択
どのような環境で主に使用するかによって、適した機種は異なります。
たとえば、
- 会議や講演が多い方
騒音抑制機能の高いモデル - 音楽鑑賞を楽しみたい方
音質重視、音楽モードのあるモデル - 活動的な方
防水・防汗性能の高いモデル - スマートフォンとの連携を重視する方
Bluetooth接続機能付きのモデル
など、ライフスタイルに合わせて選ぶことが大切です。
アフターサービスを重視
クロス補聴器は長期間使用するものです。購入店のアフターサービス体制が充実しているかも重要なポイントです。
- 定期的な調整は無料か
- 故障時の対応は迅速か
- 補聴器の保証期間
これらのポイントを事前に確認しておくことをオススメします。
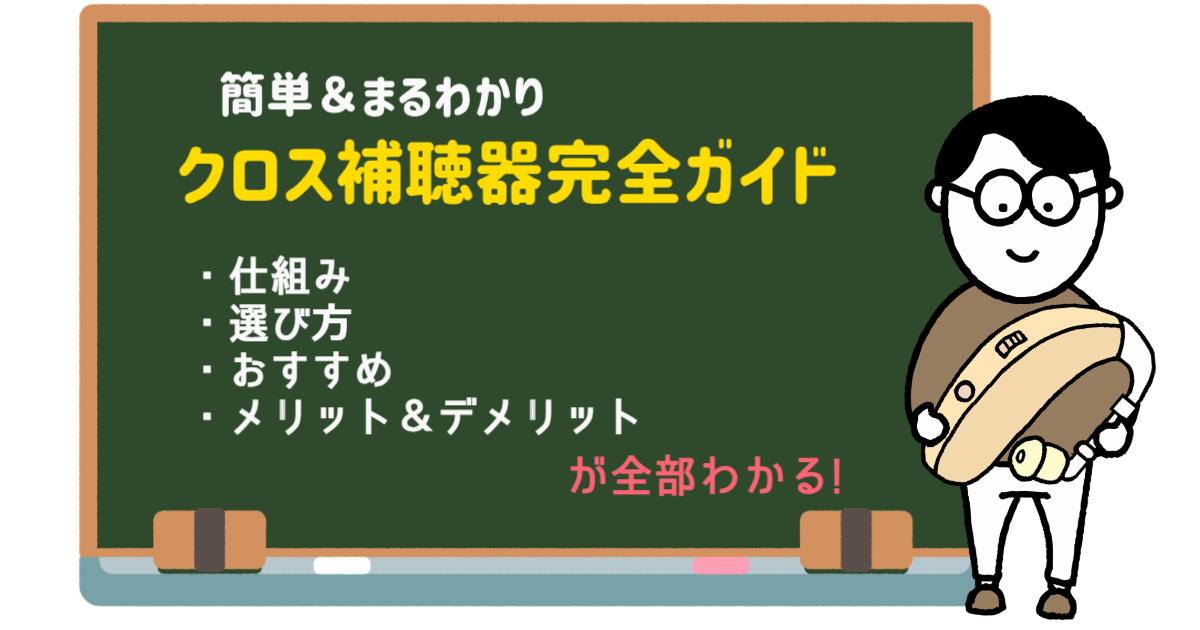
当店のクロス補聴器サポート
秋葉原補聴器リスニングラボでは、クロス補聴器をお考えの方に以下のようなサポートを提供しています。
2週間無料レンタル
当店では、クロス補聴器の2週間無料レンタルを実施しています。実際の生活の中で使用感を確かめていただけるので、購入の際の参考になります。
レンタル期間中は、「騒がしい場所での聞こえはどうか」「長時間使用しても疲れないか」など、様々なシーンでの使用感を確認していただけます。もし2週間では足りない場合は、延長することも可能です。
専門スタッフによる丁寧なカウンセリング
当店のスタッフは全員「認定補聴器技能者」の資格を持っており、専門知識を活かしてお客さま一人ひとりに寄り添ったご提案をさせていただきます。どうぞ安心してご相談ください。
「どのようなシーンで聞こえにくいと感じますか?」「趣味や仕事での会話環境はどのようなものですか?」など、詳細にお伺いすることで、より適切な提案ができると考えています。
アフターケアの充実
購入後も安心してお使いいただけるよう、定期的な調整やクリーニング、聴力測定など、きめ細かなアフターケアを提供しています。
「3~6ヶ月に一度はクリーニングにいらしてください」とお願いしているのですが、これは補聴器の性能を維持するためだけでなく、お客さまの聞こえの状況を定期的にチェックするためでもあります。
クロス補聴器と一般的な補聴器の違い
クロス補聴器と一般的な補聴器の違いを理解することも、購入を検討する上で重要です。
一般的な補聴器は、聴力が低下した耳の聞こえを補聴するもので、難聴のある耳に装着します。一方、クロス補聴器は片耳が全く聞こえない、または非常に聞こえにくい方のために開発されたシステムで、聞こえない耳側の音を聞こえる耳側に伝えるという点が大きな違いです。
一般的な補聴器を両耳に装着する「両耳装用」も一般的ですが、クロス補聴器の場合は機能的に異なる2つの装置(送信器と受信器)を使用します。
まとめ:デメリットを理解した上での判断を
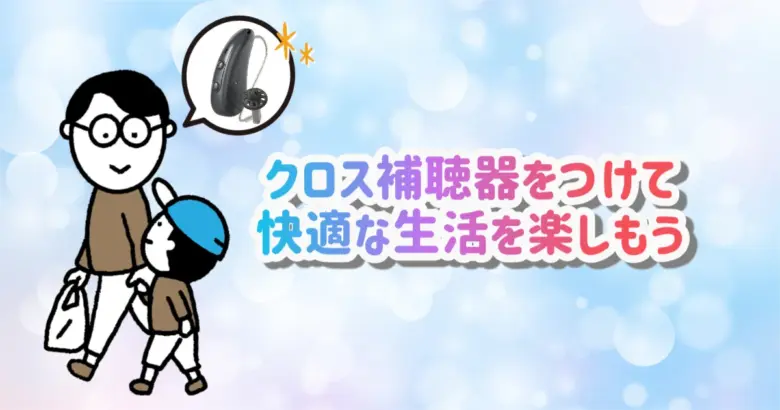
クロス補聴器には、両耳装用の必要性、音の方向感覚の問題、バッテリー消費の早さなど、いくつかのデメリットがあります。しかし、これらのデメリットを理解した上で、適切な製品を選び、正しく使用することで、片耳難聴の方の生活の質を大きく向上させることができます。
購入を検討されている方は、ぜひ無料レンタルを利用して、実際の使用感を確かめてみてください。また、補聴器専門店でアドバイスを受けながら、自分のライフスタイルに合った補聴器を選ぶことが重要です。
わたしたち秋葉原補聴器リスニングラボは、お客さま一人ひとりに寄り添い、最適な補聴器をご提案します。クロス補聴器についてのご質問やご相談は、いつでもお気軽にお問い合わせください。