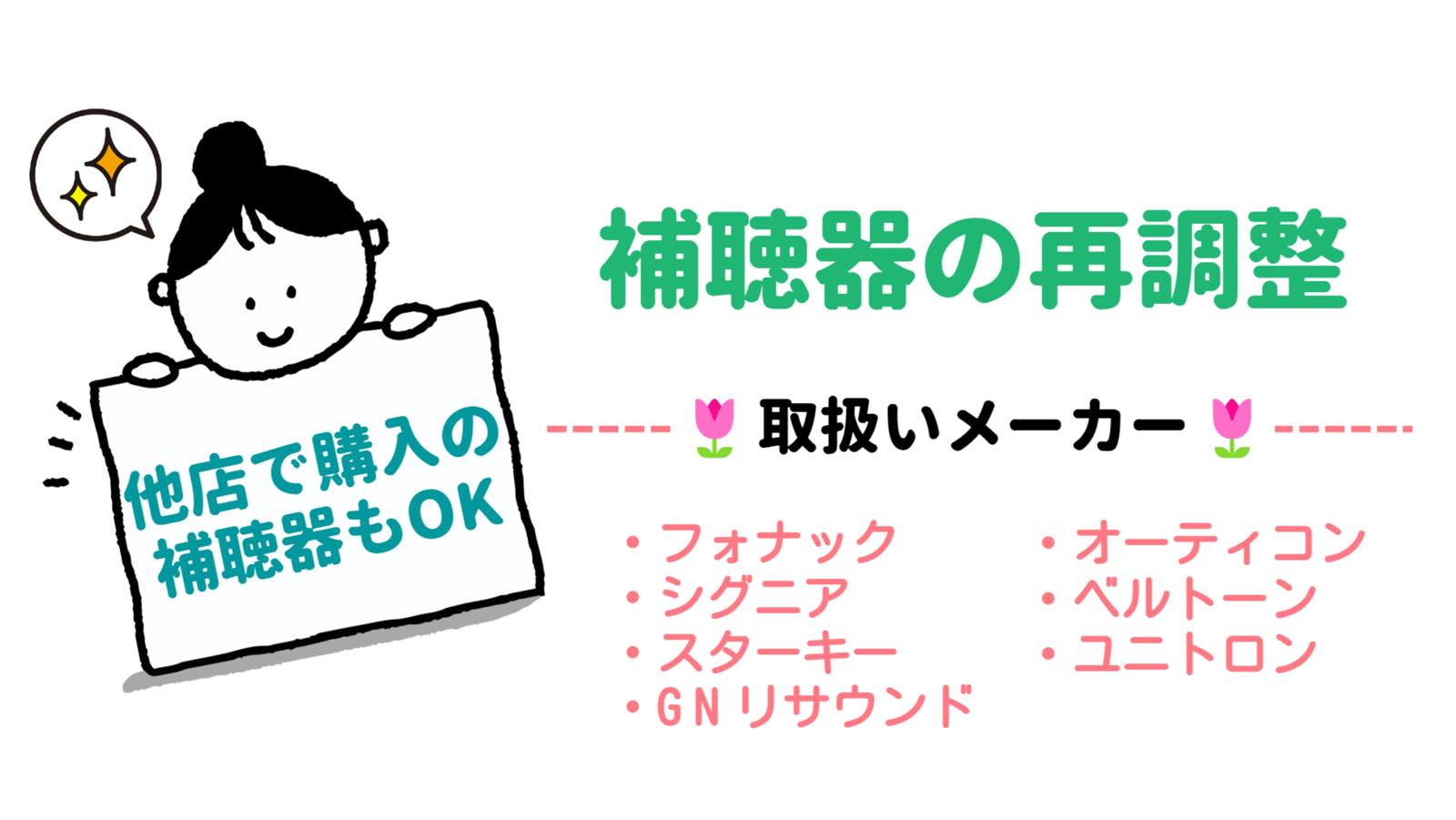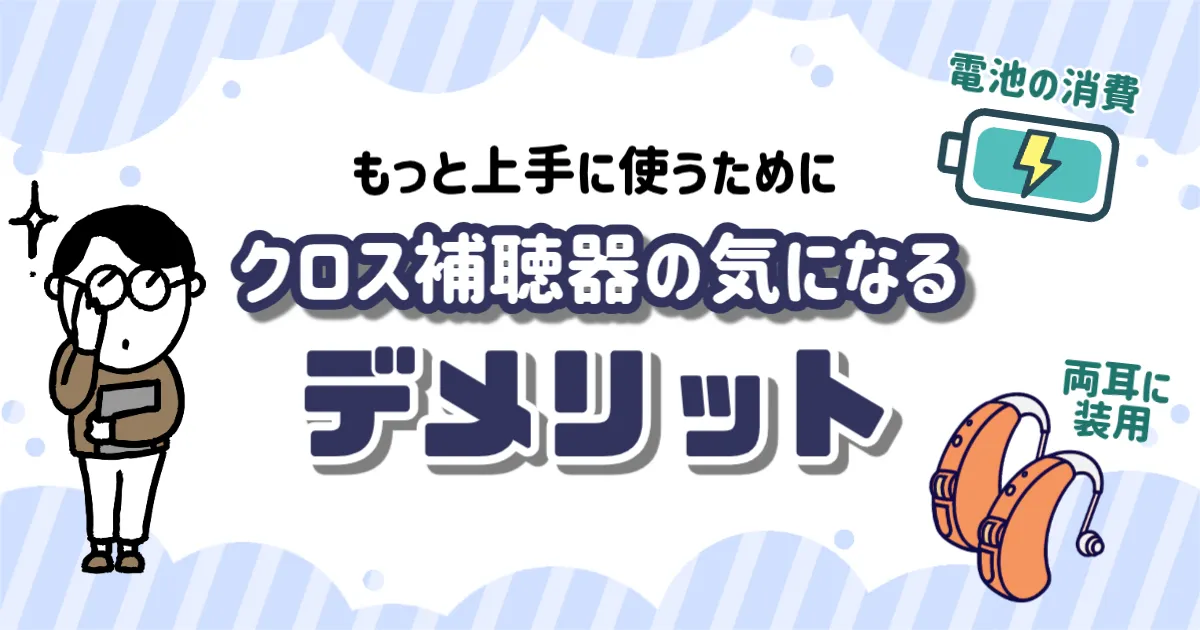こんにちは!秋葉原補聴器リスニングラボのハヤシです。今日は「クロス補聴器のデメリット」について、特に令和7年(2025年)現在の状況を踏まえてお話しします。片耳難聴でお悩みの方にとって、クロス補聴器が素晴らしい解決策となる一方で、知っておくべきデメリットもあります。「両耳装用の必要性」と「電池消費問題」を中心に、わかりやすく解説していきますね!
 たろうくん
たろうくん実はこの前、耳鼻科に行ったんだ。右耳がずっと聞こえにくくて…😟 診断されたのが『片耳難聴』だって。片耳だけ聞こえない人向けの補聴器ってあるのかな?
 みみちゃん
みみちゃんそれは大変だったね。 片耳難聴の人向けには『クロス補聴器』っていう特別な補聴器があるよ!聞こえない方の耳で拾った音を、聞こえる方の耳に届けてくれる仕組みなんだって
 たろうくん
たろうくんクロス補聴器か…でも高そうだし、買って後悔したくないんだよね😥 メリットだけじゃなくてデメリットもあるんじゃないかって心配で…自分に本当に合った補聴器を選びたいんだ。
 みみちゃん
みみちゃんその気持ち、とってもわかるよ!💡 まずは一緒にネットで調べてみよう✨️それから、補聴器専門店で相談するのもいいかも。たろうくんの生活スタイルに合った選択ができるように、わたしもサポートするね!
クロス補聴器とは?基本の仕組みを知ろう

クロス補聴器は、片方の耳の聴力が極端に低下している「片耳難聴」の方のために開発された特殊な補聴システムです。「CROS」は「Contralateral Routing of Signal(対側へ信号を送る)」の略で、その名の通り、聞こえない側から音を拾い、聞こえる側の耳に送る仕組みになっています。
こんな方に適しています
- 片方の耳が完全に聞こえなくなっている方
- 片方の耳の聴力が極端に低下している方
- 片耳に従来の補聴器を装用しても効果が得られない方
クロス補聴器の基本的な仕組みは、聞こえない耳側に「クロス補聴器(マイク)」、聞こえる耳側に「補聴器(スピーカー)」を装着します。クロス補聴器で集音した音声を、ワイヤレスで補聴器に送ることで、聞こえない側の音も聞こえる耳で聞くことができるようになります。
専門用語の解説
- CROS補聴器:片耳が完全に聞こえず、もう片方の耳が正常な方向け
- BiCROS補聴器:片耳が完全に聞こえず、もう片方の耳も聴力低下がある方向け

クロス補聴器の主なデメリット概要

この聴覚補助システムには多くのメリットがありますが、実際に使用するにあたって、いくつかのデメリットも存在します。
主なデメリットを簡単にまとめると
- 両耳装用の必要性(片耳難聴だが両耳に機器を装着する必要あり)
- コスト面の問題(両耳分の機器が必要なため初期費用が高くなる)
- バッテリー(電池)の消費が早い
- 音の方向感に関する制約
- 騒がしい環境での限界
これらのデメリットについて、順番にくわしく解説していきますね。以下の各セクションでは、これらの課題と対応策について掘り下げていきます。
両耳装用の必要性とそのデメリット
なぜ両耳装用が必要なのか
片耳難聴者向けシステムの特徴的なデメリットの一つが、両耳に装用する必要があることです。片耳難聴なのに、なぜ両方の耳に装置が必要なのでしょうか?
それは、このシステムがマイク(クロス補聴器:送信機)とスピーカー(補聴器:受信機)の2つの部分で構成されているためです。聞こえない耳側にマイクを装着し、そこで集音した音を聞こえる耳側に装着したスピーカーで再生する仕組みなのです。
見た目の懸念とその対策
両耳に補聴機器をつけることで、外見上の違和感を感じる方も少なくありません。
見た目の懸念を解消するためのポイントは…
- 小型化が進み、以前より目立ちにくくなっている
- 補聴器のカラーを髪色と合わせ、目立ちにくくする
わたしたちリスニングラボでも、見た目を気にされる方には、できるだけ目立ちにくいモデルをご提案するよう心がけています。
装用の手間と慣れるためのコツ
毎日両耳に装着する手間は、とくに朝の忙しい時間には少し面倒に感じることもあるかもしれません。両方の耳に適切に装着する必要があるので、最初は時間がかかることもあります。
慣れるためのコツとしては…
- 毎日同じ順番で装着する習慣をつける(例:右から左)
- 鏡を見ながら装着する練習をする
- 最初の1週間は少し余裕をもって準備する時間を確保する
多くの方は2週間程度で装着の手間を感じなくなり、日常の一部として自然に行えるようになります。
費用面の問題とその考え方
クロス補聴器の価格について
このシステムのデメリットとして、費用面の問題は避けて通れません。通常の補聴器と比較して高額になる理由は、両耳分の機器が必要になるからです。
片耳だけが悪いのに片耳分だけというわけにはいきません。補聴器とセットで使用することが前提となるため、両耳分必要なので価格も上がってしまいます。
長期的な視点での検討ポイント
費用面については、短期的な出費だけでなく、長期的な視点で考えることも大切です。
- 聞こえの改善による生活の質の向上
- コミュニケーションの円滑化による社会生活の充実
- 聞き逃しによるミスや誤解の減少
「両耳に装置が必要で費用が高い」というデメリットはありますが、日常生活での聞こえの改善というメリットと天秤にかけて検討することをおすすめします。実際、多くの方が装着しているときと、していないときで比較すると、装着している方が聞こえが良くなると感じられています。

電池消費問題の詳細
バッテリー寿命の実際
大きなデメリットとして、電池の消耗が早いという点があります。令和7年(2025年)現在、一般的なクロス補聴器のバッテリー寿命は、平均して約20時間程度となっています。
通常の補聴器と比べると電池寿命はやや短く、その理由は常に送受信機間で電波の送受信を繰り返すためです。
なぜ電池の減りが早いのか?
電池消費が早い理由は主に以下の点があげられます。
- 送信機と受信機の間で常に電波の送受信を行っている
- 片耳難聴用の特殊な信号処理を行っている
- Bluetooth通信ができる機種では、ワイヤレス通信を使うとさらに電池消耗が早い
これらの理由により、充電タイプは毎日の充電、電池タイプは5~7日に1度の電池交換が必要になります。
電池切れのリスクと対策
電池の減りが早いと、突然の電池切れというリスクが高まります。とくに外出先での電池切れは、コミュニケーションに支障をきたす可能性があります。
対策としては…
- 予備の電池を常に持ち歩く
- 定期的な電池交換の習慣をつける
- 電池残量インジケーターがある機種を選ぶ
- 外出前には必ず電池状態を確認する
- バッテリー内蔵の持ち運びケースを選ぶ(充電式)
充電式タイプの紹介
電池消費問題の解決策として、充電式モデルがあります。
この特徴は…
- 1日平均約20時間以上の使用が可能
- 毎日充電することで電池交換の必要がない
- 長期的には電池購入コストを削減できる
- 環境にやさしい選択肢になる
最近の補聴機器はどんどん充電式にシフトしてきており、電池の交換が面倒に感じるなら充電式で選ぶのがベストです。充電器に置くだけで使えるのでストレスなく使用可能です。
音の方向感に関する制約
方向感の欠如について
このシステムを使用する場合、すべての音が健聴耳側から聞こえるため、音の方向感が失われるというデメリットがあります。
たとえば、右耳が聞こえず左耳が健聴の場合、右側からの音も左耳で聞くことになるため、「どの方向から音が来ているのか」を感覚的に判断することが難しくなります。音の方向をつかみにくい場合があるのです。
日常生活での影響
方向感の欠如が日常生活で影響する場面としては…
- 呼びかけられた際に、どちらを向けば良いかわからない
- 車の接近音など、危険を察知するのが遅れる可能性がある
- グループでの会話で、誰が話しているのかを視覚的に確認する必要がある
これらの制約に対応するためには、視覚情報をより積極的に活用する習慣をつけることが重要です。
慣れるためのトレーニング
方向感の制約に慣れるためのトレーニング方法としては…
- 家族に協力してもらい、様々な方向から呼びかけてもらう練習をする
- 安全な環境で音源の特定練習を行う
- 視覚と聴覚を組み合わせて状況を把握する習慣をつける
多くの方は、時間をかけて徐々にこの新しい聞こえ方に適応していきます。最初は違和感があっても、脳が次第に慣れていくものです。
騒がしい環境での性能限界
静かな環境と騒がしい環境での違い
この補聴システムは静かな環境では比較的良好に機能しますが、騒がしい場所になるにつれてききとりが困難になることがあります。
これは、基本的に「聞こえない側の音をすべて聞こえる側に送る」という仕組みのため、騒音も含めてすべての音が健聴耳に届けられるからです。補聴器の性能の中に雑音抑制機能が備わっていますが、人の声だけを限定していれることはできません。結果として、騒がしい場所では必要な音(会話など)と不要な音(背景騒音)が混在して聞こえ、聞き取りづらさを感じることがあります。
対処法とコツ
騒がしい環境での聞き取りをサポートするためのコツとしては…
- 可能な限り騒音源から離れた場所に座る
- 会話相手により近い位置に移動する
- レストランなどでは壁側の席を選び、背景音を減らす
- 最新の雑音抑制機能が搭載されたハイエンドモデルを検討する
- 必要に応じて補聴援助システム(フォナック・ロジャーシステムなど)を併用する
特に令和7年(2025年)現在の最新モデルでは、より高度な雑音抑制機能を搭載したものも増えていますので、騒音下での使用が多い方は、そうした機能に注目して選ぶと良いでしょう。
最新技術による改善点(令和7年現在)
小型化と目立ちにくさの向上
令和7年(2025年)現在、技術は大きく進歩しており、以前のモデルと比べて多くの改良がなされています。とくに「両耳装用」というデメリットに関しては、機器の小型化が進み、以前より目立ちにくくなっています。
最新モデルでは
- よりコンパクトなデザイン
- 肌色や髪の色に近いカラーバリエーション
- より自然な装用感と軽量化
これらの改良により、見た目の懸念は以前よりも軽減されています。
音質と音の処理技術の進化
令和7年(2025年)現在の最新機器は、音質面でも大きな進歩を遂げています。
- より自然な音質を実現する高度な信号処理
- 聞こえない側からの音をより効果的に健聴耳に伝える技術
- 騒音下での会話理解を助ける高度なアルゴリズム
- AI技術を活用した音環境認識と最適化
これらの技術進歩により、従来のものと比較して、より快適な聞こえを実現できるようになっています。
クロス補聴器の適応条件と事前チェックポイント
どんな方に向いているのか?
とくに効果的なのは、以下のような方々です。
- 片方の耳が高度~重度難聴で、もう片方の耳が正常または軽度~中等度難聴の方
- 片方の耳に先天性の外耳道閉鎖症がある方
- 片方の耳が突発性難聴などで聴力を失った方
- 片側性の聴神経腫瘍などで聴力が低下している方
購入前に確認すべきポイント
購入を検討されている方は、以下のポイントを事前に確認されることをおすすめします。
- 両耳の正確な聴力検査結果
- 日常生活での聞こえの困りごとの具体的な場面
- 予算と長期的な維持費(電池代など)
- 試聴体験の可能性(当店では無料でお試しいただけます)
- アフターサービスの内容と保証期間
とくに試聴やレンタルは非常に重要です。実際の使用感を体験し、デメリットまで理解した上で判断できます。
医療機関との連携の重要性
選択にあたっては、医療機関との連携も重要です。
- 耳鼻咽喉科での正確な診断
- 難聴の原因や進行可能性の確認
- 補聴器適合判定(補聴器相談医)の活用
- 定期的な聴力モニタリング
医療機関と連携することで、より安全で効果的な聴覚リハビリテーションを進められます。
実際のユーザーの声と対処法
デメリットへの対応例
実際にクロス補聴器を使用されているお客様からは、デメリットについて以下のような声をいただいています。
「両耳に装置をつける必要があるのが面倒」
→多くの方は2週間程度で慣れることが多いです。初めのうちは自宅で練習することもおすすめします。
「電池の減りが早くて困る」
→充電式モデルへの切り替えで解決されるケースが多いです。電池式の場合は、予備の電池を常に持ち歩く習慣をつけましょう。
「方向感がつかみにくい」
→クロス補聴器を使用しながら、徐々に慣れていく方が多いです。また、視覚情報を積極的に活用することも効果的です。
リスニングラボでの対応事例
当店では、クロス補聴器のデメリットに対して、以下のようなサポートを行っています。
- 最初の装用指導でしっかりと使い方をレクチャー
- 定期的な聞こえの確認と調整
- 必要に応じた追加アクセサリーの提案
とくに「慣れるまでの期間」をしっかりとサポートすることで、デメリットを最小限に抑えられるよう心がけています。
令和7年、最新のクロス補聴器選びのポイント
価格帯と機能の関係
クロス補聴器の価格は、約10~15万円です。聞こえる側につける補聴器の性能によって、聞きやすさ(音質)が変わります。補聴器の価格帯は大きく分けて3つあります。
- エントリークラス(片耳あたり10〜15万円程度)
基本機能は備えているが、騒音抑制などの高度な処理は限定的 - ミドルクラス(片耳あたり15〜25万円程度)
騒音抑制や方向性マイクなど、より高度な機能を搭載 - プレミアムクラス(片耳あたり25万円以上)
音質がさらに良く、自動環境認識機能などの高度な機能を搭載
選ぶ際のチェックリスト
選びで重視すべきポイントをまとめました
- 充電式か電池式か(電池の取り扱いの手間を考慮)
- Bluetooth機能の有無(スマホと連携したい方向け)
- 防水・防塵性能(アクティブなライフスタイルの方向け)
- アフターサービスの充実度(定期的なメンテナンスの重要性)
- 試聴の結果(実際の装用感や音質が最も重要)
- メーカーの保証内容(長く安心して使うために)
これらのポイントをチェックしながら、自分に最適なクロス補聴器を選びましょう。
メンテナンスと長期使用のポイント
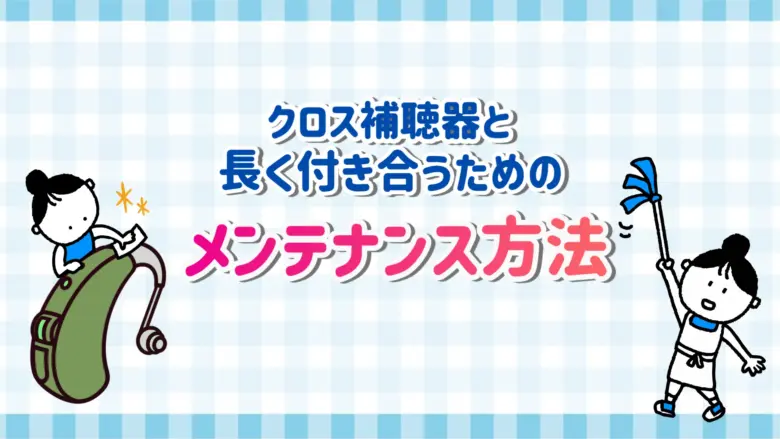
日常のお手入れ方法
長く快適に使用するためには、日常的なお手入れが欠かせません。
- 就寝前(補聴器使用後)に柔らかい布で本体を拭く
- 耳あか防止フィルターの定期的な交換
- 充電端子の清掃(充電式の場合)
- 湿気対策として乾燥ケースの使用
- 汗をかいた後は特に丁寧に拭きとる
とくに、両耳に装着するこの補聴システムは、ケアも2台分必要になるため、お手入れの習慣をしっかりとつけることが大切です。
定期メンテナンスの重要性
長期間にわたって性能を維持するために、定期的に補聴器店へメンテナンスにいくことも重要です。
- 3〜6ヶ月に一度の動作チェック
- 音質や音量の微調整
- 外部マイクの清掃
- 内部回路のチェック
- 必要に応じた部品交換
当店では、購入後のアフターケアも充実させており、定期的なメンテナンスで長く快適にお使いいただけるようサポートしています。
トラブル時の対応法
よくあるトラブルとその対処法をご紹介します。
「音が聞こえなくなった」
→電池切れや充電切れを確認。耳あか詰まりの可能性も。
「音が途切れる」
→送信機と受信機の距離が離れすぎていないか確認。マイクの汚れもチェック。
「音がひずむ」
→音量設定の確認。マイク部分の汚れを清掃。
「充電できない」
→充電端子の清掃。充電器本体のコンセント接続を確認。
緊急時には当店にご連絡ください。電話でのアドバイスも行っております。
まとめ:クロス補聴器のデメリットを理解した上での選択

デメリットを超えるメリット
クロス補聴器には確かにいくつかのデメリットがありますが、片耳難聴の方にとっては、それを上回るメリットがあります。
- 聞こえない側からの音も聞き逃さなくなる
- 全方向からの警告音やアナウンスに気づける
- 会話の聞き取りが向上する
- 社会生活や仕事での安心感が増す
デメリットを理解した上で上手に使いこなせば、生活の質を大きく向上させることができますね!
個別相談の重要性
このクロス補聴システムが自分に合っているかどうかは、実際に試してみないとわかりません。当店では、個別の聞こえの状況に合わせた丁寧な相談と試聴・レンタルを行っています。
- ライフスタイルに合わせた機種の提案
- デメリットも含めた正直な説明
- 実際の使用環境で試せるレンタルサービス
- アフターフォロー計画の提案
「片耳が聞こえない」という同じ状態でも、人によって最適な補聴器は異なります。ぜひ補聴器専門店でご相談ください。
秋葉原補聴器リスニングラボからのメッセージ
当店では「聞こえの悩みを抱えている方に最適な解決策を提供したい」という思いで、日々お客様と向き合っています。クロス補聴器のデメリットについても正直にお伝えした上で、それをカバーする方法もしっかりとご提案いたします。
片耳難聴でお悩みの方、「補聴器をつけても効果がない」と諦めていた方、ぜひ一度ご相談ください。最新のクロス補聴器で、新しい聞こえの世界が広がるかもしれません。ご不明な点があれば、いつでもお気軽にご質問ください!