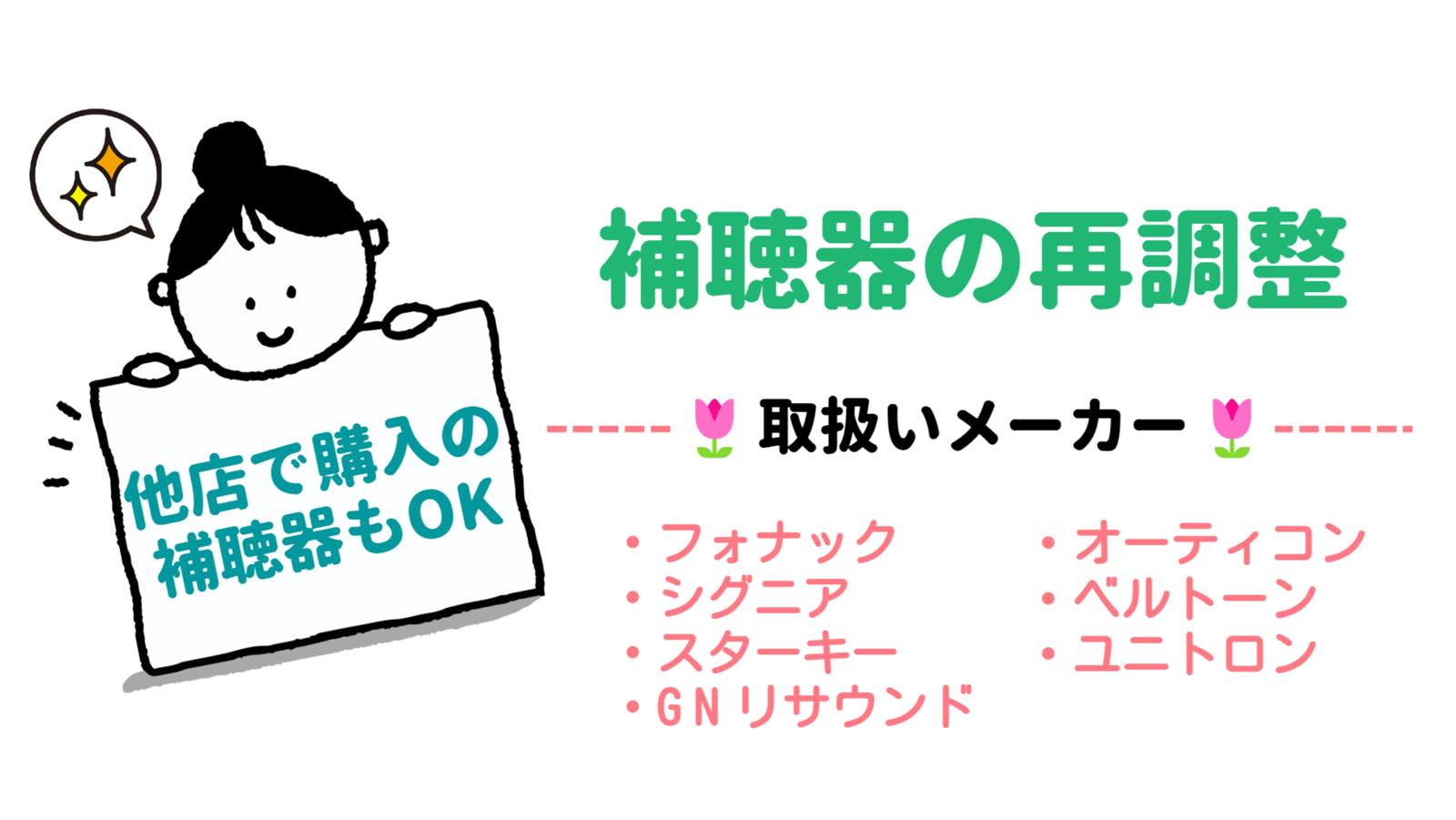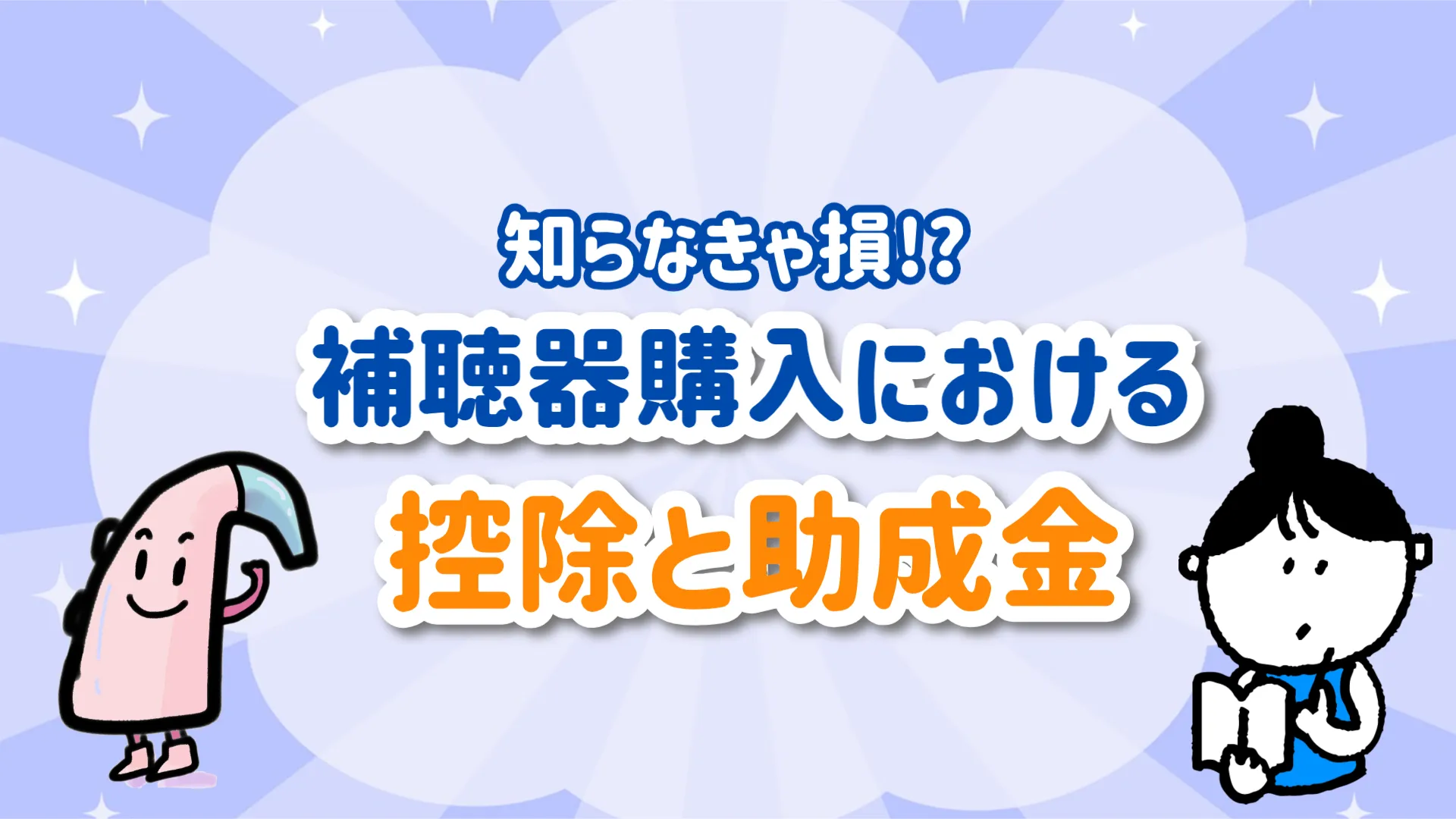こんにちは!秋葉原補聴器リスニングラボのハヤシです。
「補聴器って高いけど、保険は使えないの?」「何か費用を安くする方法はないの?」
このようなご質問を、お客さまから本当によくいただきます。確かに補聴器は決して安い買い物ではありませんし、保険が使えるかどうかは重要なポイントですよね。
結論から申し上げますと、残念ながら補聴器の購入には健康保険や介護保険は適用されません。しかし、諦める必要はありません!じつは、費用負担を軽減できる制度がいくつか存在するんです。
今回は、補聴器購入時に利用できる助成制度や医療費控除について、令和7年の最新情報をもとに詳しく解説いたします。
 たろうくん
たろうくん耳が聞こえにくくて耳鼻科に行ったら、難聴で補聴器が必要と言われたの。でも補聴器って高額なんだよね…😟
 みみちゃん
みみちゃんそれは大変ね💦 補聴器って15万円くらいするもんね😭でも安心して!実は補聴器には助成金制度があるのよ✨ 障害者手帳をもってると、自己負担が1割になったり、自治体によっては独自の補助金もあるの💡
 たろうくん
たろうくんえ、そうなの?😲 でも申請が大変そうで…手続きも複雑そうで不安だよ😰 失敗して損したらどうしよう。ちゃんと調べてから進めないと心配で…
 みみちゃん
みみちゃんまずは、ネットで調べてみよう!住んでいる自治体のホームページを見れば、助成金制度の詳細が分かるから✨ 一人で悩まないでね、一緒に調べるよ💪

補聴器の保険適用の現状
まず、多くの方が気になる「補聴器に保険は使えるのか」という疑問についてお答えします。
現在の制度では、補聴器購入に健康保険や介護保険を適用することはできません。これは補聴器が医療機器ではなく、福祉用具として分類されているためです。
補聴器の平均購入価格は約15万円と非常に高価なため、保険が適用されないことで購入をためらわれる方も多いのが現実です。
しかし、次にご紹介する制度を活用することで、費用負担を大幅に軽減することが可能です。
利用できる助成制度の種類
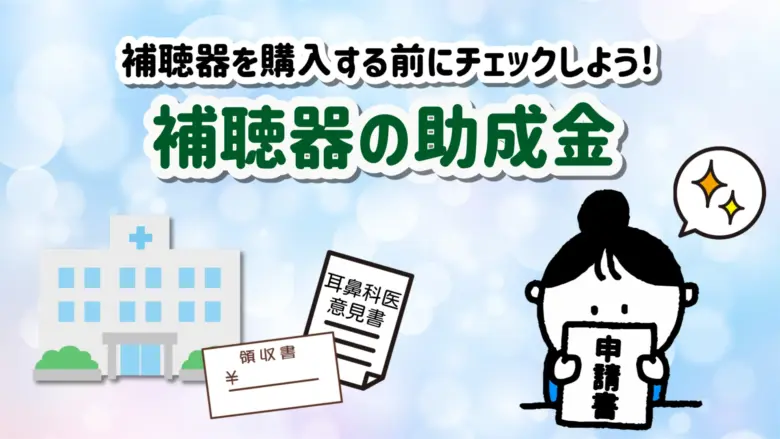
補聴器購入時に利用できる助成制度は、主に以下の3つに分けられます
- 障害者総合支援法による補装具費支給制度
- 自治体独自の補聴器購入費助成制度
- 医療費控除
それぞれについてくわしく見ていきましょう。
障害者総合支援法による補装具費支給制度
制度の概要
障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度は、聴覚障害で身体障害者手帳をお持ちの方が対象となる制度です。
この制度では、補聴器購入費用の原則1割が利用者負担となり、残りの9割は公費で賄われます。
対象となる方
対象となるのは以下の条件を満たす方です
- 聴覚障害による身体障害者手帳をお持ちの方
- 高度難聴レベル(概ね70デシベル以上)以上の聴力損失がある方
- 耳鼻咽喉科医師による判定で補聴器が必要と認められた方
支給される補聴器の基準価格
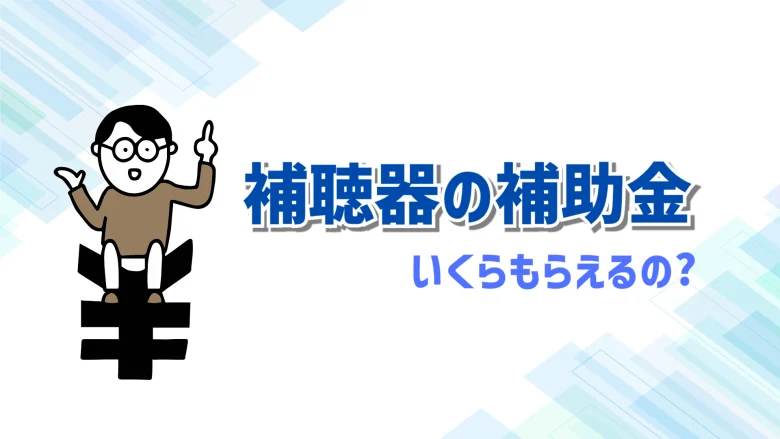
補聴器補助金を申請した場合、補助金の額は障害者手帳の等級や補聴器の種類によって異なります。障害者総合支援法で支給される補助金額は、以下になります。
| 障害者手帳の等級 | 補聴器の種類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2級・3級 (重度難聴) | 耳かけ型 | 71,200円 |
| ポケット型 | 59,000円 | |
| 4級・6級 (高度難聴) | 耳かけ型 | 46,400円 |
| ポケット型 | 44,000円 | |
| すべての等級 | 耳あな型(オーダーメイド) | 144,900円 |
| 耳あな型(既製品) | 92,000円 | |
| 骨伝導式メガネ型 | 126,900円 |
交付が決定すると、現金ではなく「補装具費支給券」が発行され、金額相当の補聴器と交換になります。また、原則1割の自己負担があります。補聴器の購入だけでなく、故障したさいの修理費用も申請が可能です。
自治体独自の補聴器購入費助成制度
多くの自治体では、身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度難聴の方向けに、独自の補聴器購入費助成制度を設けています。
東京都内の助成制度例
令和7年現在、東京都内の各区では以下のような助成制度が実施されています。
品川区
- 対象:65歳以上、中等度難聴(40~70デシベル未満)の方
- 助成額:上限72,450円(令和7年4月より35,000円から引き上げ)
港区
- 対象:60歳以上の方
- 助成額:上限144,900円(住民税課税の方は上限72,450円)
台東区
- 対象:65歳以上の方
- 助成額:住民税非課税の方144,900円、住民税課税の方72,450円
千代田区
- 対象:60歳以上の方(令和7年7月から新制度開始)
- 助成額:住民税課税世帯72,450円、住民税非課税世帯144,900円
自治体助成制度の共通する条件
多くの自治体の助成制度では、以下のような共通条件があります。
- 耳鼻咽喉科医師による補聴器装用の必要性の認定
- 聴覚障害による身体障害者手帳の非対象者
- 過去に同様の助成を受けていない、または一定期間(通常5年)が経過している
- 助成決定前の購入は対象外
購入店の要件
助成制度を利用する場合、多くの自治体では以下のいずれかの要件を満たす店舗での購入が条件となっています。
- 認定補聴器技能者在籍店
- 認定補聴器専門店
- 医療機関の補聴器外来
医療費控除について
医療費控除の対象となる条件
補聴器購入費用は、一定の条件を満たせば医療費控除の対象となります
医療費控除の対象となるのは、「医師の診断に基づいて、治療に必要と認められた補聴器」に限られます。
具体的には以下の条件が必要です。
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定の補聴器相談医を受診
- 医師による「補聴器適合に関する診療情報提供書」の作成
- 治療目的での購入であることの明確化
医療費控除を受けるための手続き
医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。たとえば2024年1月1日から12月31日に支払った分の医療費控除を受けたい場合は、2025年2月17日から3月17日までに確定申告を行う必要があります。
必要な書類は以下の通りです
- 医療費控除の明細書
- 補聴器適合に関する診療情報提供書
- 補聴器の領収書
注意点
以下のような場合は医療費控除の対象になりません
- 家電量販店やインターネット通販での購入(必要書類の発行ができない場合)
- 治療以外の目的(音楽鑑賞など)での購入
- 医師の診断がない場合

助成制度利用の手続きの流れ
障害者総合支援法の場合
- 耳鼻咽喉科での診断・意見書作成
- 市区町村の障害福祉課への相談
- 身体障害者手帳の申請・取得
- 補装具費支給申請書の提出
- 判定(必要に応じて更生相談所での判定)
- 支給決定・補聴器の購入
自治体独自制度の場合
- 耳鼻咽喉科での診断・証明書作成
- 市区町村の担当課への事前相談
- 助成申請書の提出
- 審査・助成決定
- 指定店舗での補聴器購入
- 助成金の交付
重要なポイント
多くの自治体では助成決定前の購入は対象外となるため、必ず事前に申請手続きを行ってください
制度選択のポイント
複数の制度が利用できる場合の選択のポイントをご紹介します。
聴力レベルによる選択
- 高度~重度難聴(70デシベル以上)
→ 障害者総合支援法 - 中等度難聴(40~70デシベル)
→ 自治体独自制度を検討 - 軽度難聴(25~40デシベル)
→ 医療費控除や一部自治体制度
年齢による選択
- 65歳以上
多くの自治体制度が利用可能 - 60歳以上
港区、千代田区などで制度利用可能 - 18歳以上
一部自治体や医療費控除を検討
よくある質問と注意点
複数の制度は併用できますか?
基本的に、障害者総合支援法と自治体独自制度の併用はできません。
両耳に補聴器が必要な場合は?
多くの自治体制度では片耳1台が基本ですが、世田谷区のように両耳購入時の上限額を設定している自治体もあります。
修理費用も助成対象になりますか?
障害者総合支援法では修理費用も支給対象となります。自治体制度については各自治体にお問い合わせください。
耐用年数はありますか?
障害者総合支援法で支給される補聴器の耐用年数は5年と定められています。そのため、福祉制度を利用して補聴器の再支給や買い替えを申請できるのは、原則として5年ごととなります。
ただし、耐用年数はあくまで目安であり、使用状況や故障の内容によっては5年未満でも修理や再支給が認められる場合もあります。
申請時の注意点
事前相談の重要性
どの制度も事前相談が重要です。とくに自治体独自制度では、助成決定前の購入は対象外となるため、必ず購入前にご相談ください。
必要書類の準備
医師の診断書や証明書の作成には時間がかかる場合があります。余裕をもって手続きを進めましょう。
予算の制約
自治体によっては年間予算に限りがあり、申請が集中すると交付決定まで時間がかかる場合があります。
まとめ

補聴器は確かに健康保険や介護保険の適用外ですが、さまざまな助成制度や控除制度を活用することで、費用負担を大幅に軽減することが可能です。
とくに令和7年は多くの自治体で制度の拡充や新設が行われており、より多くの方が支援を受けられる環境が整っています。
重要なのは、ご自身の状況に最も適した制度を選択し、正しい手続きを行うことです。聴力レベル、年齢、所得状況、お住まいの地域によって利用できる制度が異なりますので、まずは専門家にご相談いただくことをオススメします。
わたしたち秋葉原補聴器リスニングラボでも、各種助成制度についてのご相談を承っております。お客さま一人ひとりの状況に応じて、最適な制度活用方法をご提案いたします。
補聴器の購入を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。適切な制度を活用して、より良い聞こえの実現をサポートさせていただきます。
※制度の詳細や最新情報については、各自治体の担当窓口にお問い合わせいただくか、当店までご相談ください。