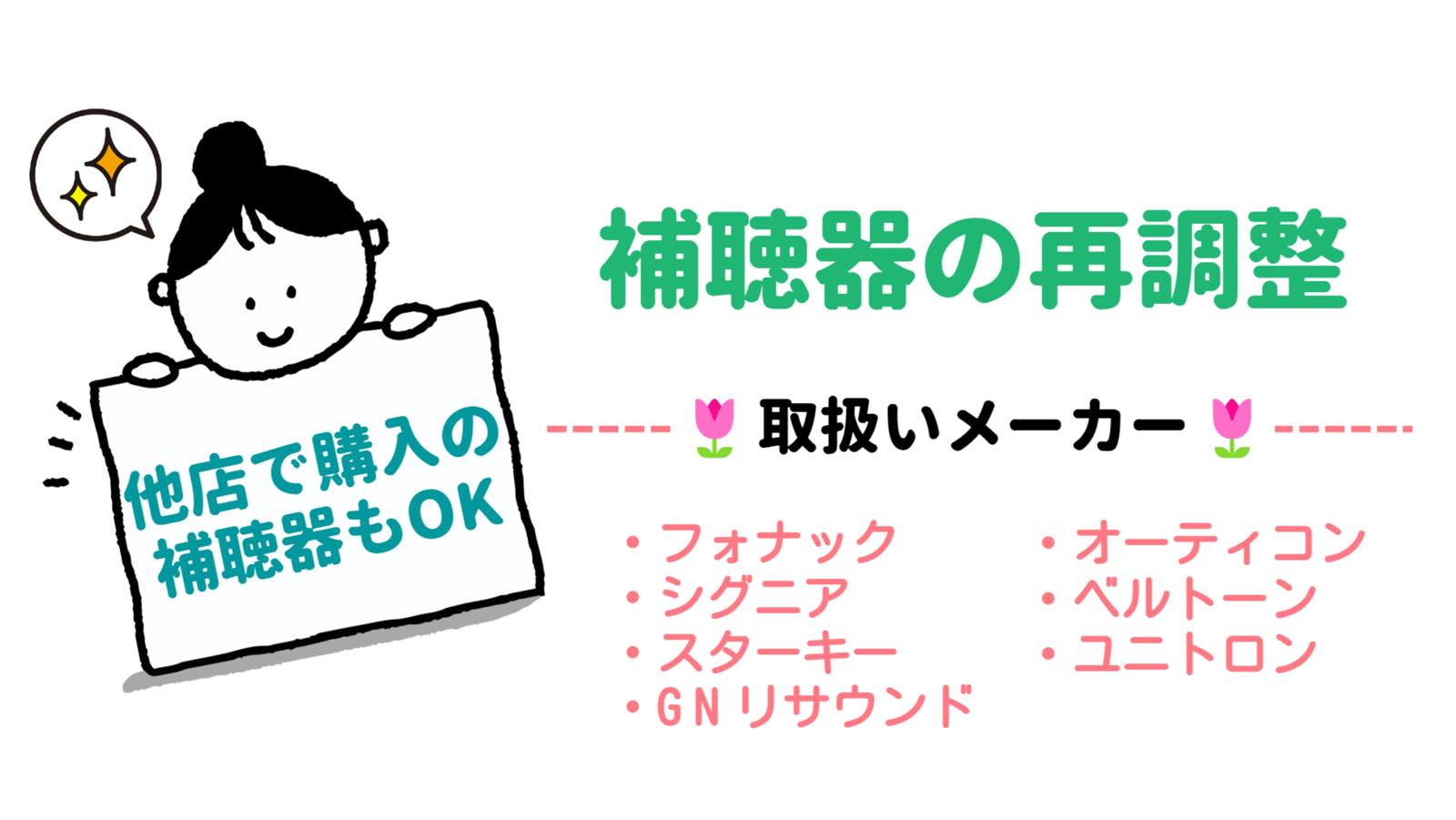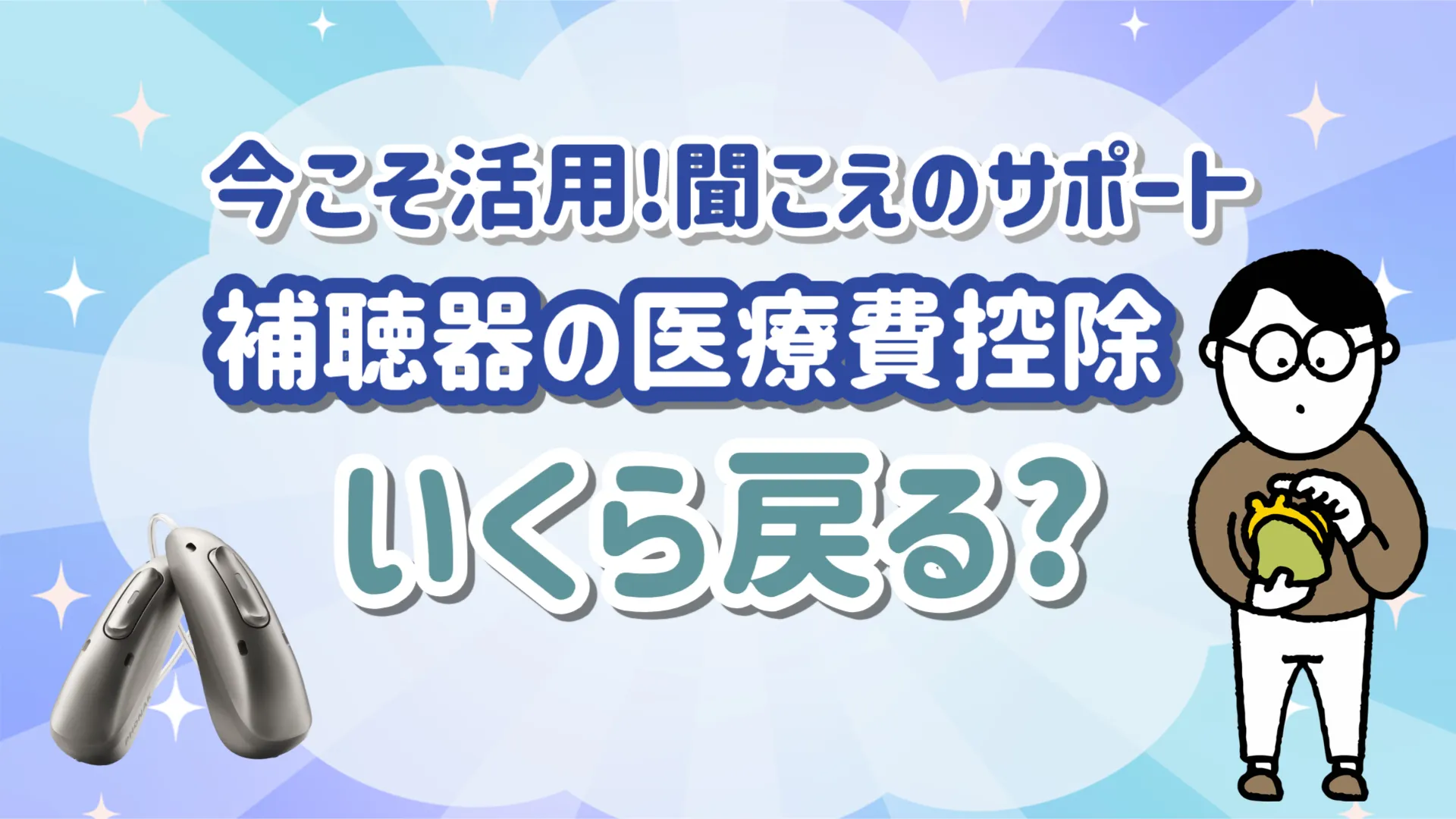こんにちは!秋葉原補聴器リスニングラボのハヤシです。最近、お客さまから「補聴器を買ったら医療費控除でお金が戻ってくるって聞いたけど、実際はどのくらい戻るの?」というご質問をよくいただきます。
補聴器は決して安いお買い物ではありませんから、少しでも費用を抑えられるなら活用したいですよね。そこで今回は、2025年の最新情報をもとに、補聴器購入時の医療費控除について、どのくらいの金額が戻ってくるのかを詳しく解説していきます!
 たろうくん
たろうくん耳が聞こえにくくて耳鼻科に行ったら、難聴で補聴器が必要と言われたんだ…😰
でも補聴器って高額なんだよね…どうしよう💦
 みみちゃん
みみちゃん大変だったね💦補聴器って15万円くらいするもんね😢
そういえば、補聴器って医療費控除の対象だって知ってた?💡活用できると嬉しいよね!
 たろうくん
たろうくんえ、本当?😲医療費控除って使えるの?でも手続きとか複雑そうで失敗したらどうしよう😅それに、いくらくらい戻るのか知りたいな💭
 みみちゃん
みみちゃん大丈夫よ、たろうくん😊1つずつ丁寧に確認してみよう✨️まずは、ネットで医療費控除の流れをチェックしてみましょう!

補聴器が医療費控除の対象になったのはいつから?
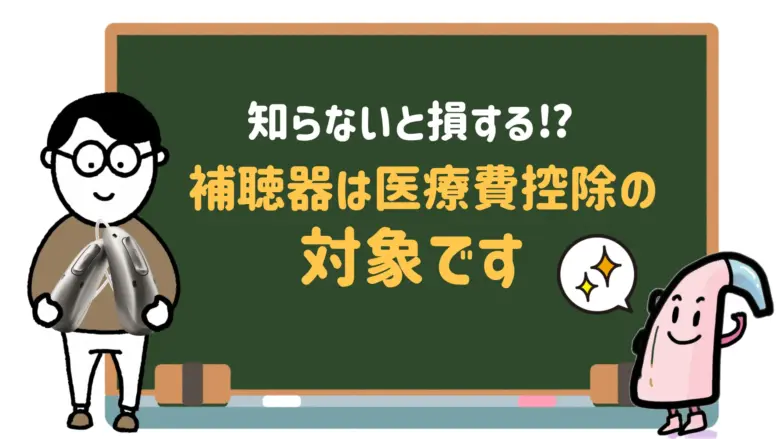
じつは、補聴器の購入費用が医療費控除の対象になったのは比較的最近のことなんです。
2018年度(平成30年度)から、財務省が正式に認定し、補聴器の購入費用が医療費控除の対象となりました。それまでは、全国統一の基準がなく、各税務署の判断に委ねられていたため、地域によって対応が異なっていました。
つまり、7年前から補聴器購入費用の医療費控除が全国で統一的に受けられるようになったということですね。
医療費控除を受けるための条件
補聴器を購入した方すべてが医療費控除を受けられるわけではありません。いくつかの条件をクリアする必要があります。
補聴器相談医の診断が必須
医療費控除を受けるためには、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定の補聴器相談医による診断が必要です。
補聴器相談医は、専門のカリキュラムを履修した耳鼻咽喉科医で、いわば「難聴や補聴器のスペシャリスト」です。この医師が、あなたの聴力検査を行い、補聴器が治療に必要と判断した場合に、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を作成してくれます。
治療目的での購入であること
大切なのは、補聴器の購入が治療目的であることです。
「音楽を楽しむため」や「ワイヤレスイヤホン的な使用」など、治療以外の目的で購入した場合は対象外となります。あくまでも、治療の一環として、医師が補聴器の使用を認めた場合のみ対象となります。
認定店舗での購入が必要
補聴器を購入する店舗にも条件があります。医療費控除の対象となるのは、以下の店舗で購入した場合のみです。
- 認定補聴器専門店
- 認定補聴器技能者が在籍している販売店
メガネ店に併設されている補聴器ショップなどは、これに該当しない場合もあるので注意が必要です。
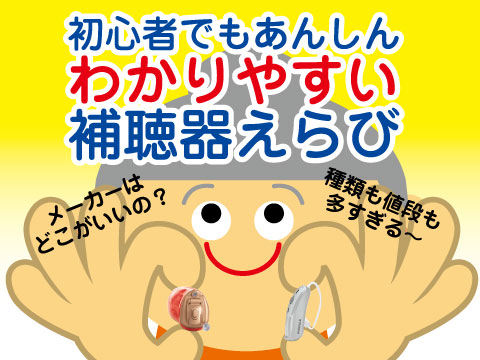
医療費控除を受けるための手順
医療費控除を受けるには、正しい手順を踏む必要があります。順番を間違えると控除が受けられない場合もあるので、しっかりチェックしておきましょう。
補聴器相談医を受診する
まず最初に、補聴器相談医を受診します。
診察を受けて補聴器が必要と診断された場合、医師が「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を作成してくれます。この書類は、医療費控除を受けるための必須書類となります。
診療情報提供書を持参して補聴器販売店へ
次に、医師から受け取った「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を持参して、認定補聴器専門店または認定補聴器技能者が在籍する販売店を訪れます。
店舗では、あなたの聞こえにあわせた補聴器を選定・試用し、最適な調整を行います。購入時には、販売店から領収書と診療情報提供書の写しが発行されますので、必ず受け取ってください。
確定申告で医療費控除を申請
補聴器を購入した年度の確定申告で、医療費控除の申請を行います。
確定申告の際、税務署から「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の写しと領収書の提出を求められることがあります。また、申請後も、これらの書類は5年間保管する必要があります。
実際に戻ってくる金額の計算方法
さて、ここからがみなさんが一番気になる部分だと思います。実際にどのくらいの金額が戻ってくるのか、計算方法を詳しく説明しますね。
医療費控除の基本計算式
医療費控除は、以下の計算式で算出されます。
医療費控除額 = [支払った医療費の合計 – 保険金等で補填された金額] – 10万円(または総所得金額の5%)
ここで重要なのは、この計算で出た金額が実際に戻ってくる金額ではないということです。これは「控除額」であり、実際の返金額は、この控除額に所得税率をかけた金額になります。
実際の返金額の計算
実際に戻ってくる金額は、以下のように計算します。
返金額 = 医療費控除額 × 所得税率
所得税率は、課税所得によって以下のように決まっています。
| 課税所得額 | 所得税率 |
|---|---|
| 195万円未満 | 5% |
| 195万円以上330万円未満 | 10% |
| 330万円以上695万円未満 | 20% |
| 695万円以上900万円未満 | 23% |
| 900万円以上1,800万円未満 | 33% |
| 1,800万円以上4,000万円未満 | 40% |
| 4,000万円以上 | 45% |
住民税の減税も忘れずに
じつは、医療費控除による恩恵は所得税の還付だけではありません。翌年度の住民税も減税されます。住民税は一律10%の税率で計算されるため、医療費控除額の10%が住民税から減額されます。
つまり、実際の節税効果 = 所得税の還付 + 住民税の減税となります。
具体的な金額例で理解しよう
計算式だけでは分かりにくいので、具体的な例で見てみましょう。
例1:課税所得280万円の方が20万円の補聴器を購入
- 医療費控除額:20万円 – 10万円 = 10万円
- 所得税の還付:10万円 × 10% = 1万円
- 住民税の減税:10万円 × 10% = 1万円
- 合計節税効果:2万円
例2:課税所得300万円の方が15万円の補聴器を購入
- 医療費控除額:15万円 – 10万円 = 5万円
- 所得税の還付:5万円 × 10% = 5,000円
- 住民税の減税:5万円 × 10% = 5,000円
- 合計節税効果:1万円
例3:課税所得500万円の方が30万円の補聴器を購入
- 医療費控除額:30万円 – 10万円 = 20万円
- 所得税の還付:20万円 × 20% = 4万円
- 住民税の減税:20万円 × 10% = 2万円
- 合計節税効果:6万円
このように、所得が高いほど、また補聴器が高額なほど、節税効果も大きくなります。
医療費控除の注意点とポイント
年間の医療費を合算できます
医療費控除は、補聴器だけでなく、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費の合計で計算します。
つまり、他の医療費と合算して10万円を超えた場合、その超えた分が控除対象となります。たとえば、補聴器が8万円、他の医療費が3万円の場合、合計11万円となり、1万円が控除対象となります。
家族の医療費も合算可能
医療費控除は、本人だけでなく、生計を一にする家族の医療費も合算できます。つまり、ご夫婦や親子で医療費を合算することで、控除額を増やすことができます。
確定申告の時期について
医療費控除を受けるには確定申告が必要です。
たとえば、2024年1月1日から12月31日に支払った医療費控除を受けたい場合は、2025年2月17日から3月17日までに確定申告を行う必要があります。
年金受給者も対象になります
高齢者や年金受給中の方でも、確定申告をすれば医療費控除を受けることが可能です。
ただし、医療費控除は「所得税や住民税の控除が受けられる制度」ですので、すでに所得税や住民税が非課税の方は、控除を受けることができません。
対象外となるもの
以下のものは、基本的に医療費控除の対象外となります。
- 補聴器の電池代
- 補聴器の修理費用
- 集音器の購入費用
医療費控除の対象となるのは、補聴器本体の購入費のみです。
よくある質問
Q: 補聴器を2個購入した場合はどうなりますか?
A: 医師が両耳の補聴器が必要と診断し、診療情報提供書に記載されていれば、両耳分の購入費用が医療費控除の対象となります。
Q: 補聴器を買い替えた場合も控除の対象になりますか?
A: はい。医師が新しい補聴器が必要と診断し、診療情報提供書を作成してもらえれば、買い替えの場合も控除の対象となります。
Q: 集音器は医療費控除の対象になりますか?
A: いいえ。集音器は医療機器ではないため、医療費控除の対象外です。あくまでも、医療機器として認定された補聴器のみが対象となります。
Q: 医療費控除の申請を忘れた場合、後から申請できますか?
A: はい。医療費控除は5年間遡って申請することができます。過去5年以内に補聴器を購入した方は、まだ申請が可能です。
医療費控除を最大限活用するためのコツ
家族の医療費をまとめて管理
医療費控除を最大限活用するためには、家族全員の医療費をまとめて管理することが大切です。レシートや領収書を一箇所に保管し、年末に合計金額を計算してみましょう。
医療費控除のシミュレーションを活用
インターネットには、医療費控除のシミュレーションツールがたくさん公開されています。購入前に、どのくらいの節税効果があるかを計算してみることをおすすめします。
購入時期の調整
医療費控除は年単位で計算されるため、購入時期を調整することで控除額を最大化できる場合があります。例えば、他の医療費と合わせて10万円を超えるよう購入時期を調整するなどです。
まとめ:医療費控除で、かしこく補聴器

補聴器の医療費控除について、詳しく解説してきました。重要なポイントをまとめると
医療費控除を受けるための条件
- 補聴器相談医の診断が必要
- 治療目的での購入であること
- 認定店舗での購入が必要
手続きの流れ
- 補聴器相談医を受診
- 診療情報提供書を持参して補聴器を購入
- 確定申告で医療費控除を申請
実際の節税効果
- 所得税の還付 + 住民税の減税
- 課税所得や購入金額によって変動
- 一般的に購入金額の10-30%程度
補聴器は決して安いお買い物ではありませんが、医療費控除を活用することで、実質的な負担を軽減することができます。条件を満たす方は、ぜひ活用してみてくださいね。
秋葉原補聴器リスニングラボでは、補聴器の選び方から医療費控除の手続きまで、丁寧にサポートさせていただいています。ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
みなさんの聞こえの改善と、少しでもお得に補聴器をご購入いただけるよう、全力でサポートいたします!